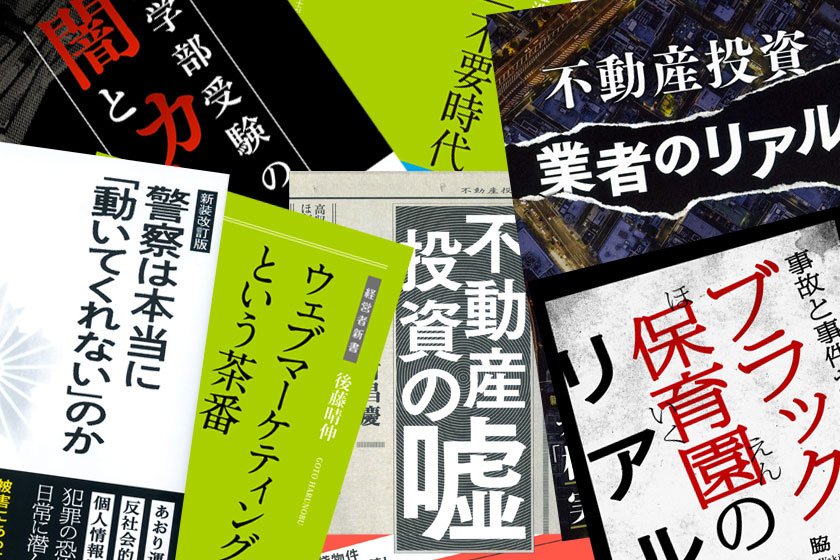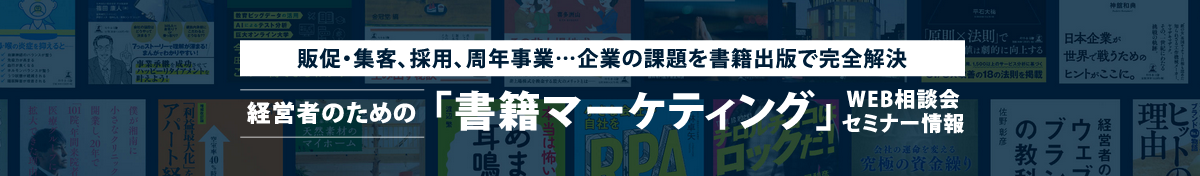周年記念事業を成功に導く 押さえておきたい社史・年史の作り方【第二回 業者選定編】
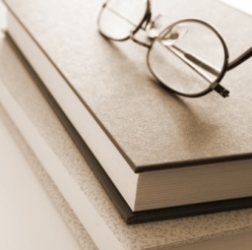
社史・年史制作を行う担当の方が抱える課題や疑問の解決のため、制作に向けて押さえておくべきポイントをご紹介する本コラム。第二回は社史・年史の制作を依頼する業者の選定についてです。
<第一回についてはこちら> 周年記念事業を成功に導く 押さえておきたい社史・年史の作り方【第一回 コンセプト編】
社史・年史を制作する際には必ず予算とスケジュールのガイドラインを作成する必要がありますが、担当者の方一人では予算感や必要な制作期間は判断ができないため、制作を依頼する会社と検討を進める必要があります。社史・年史を制作する会社は出版社と印刷会社がありますが、その違いは何なのか。その違いを以下でご紹介致します。
出版社と印刷会社の違い
・費用感の違い 制作に関する費用感は構成や印刷する部数によりますし、出版社ごと、印刷会社ごとにも違いはありますが、出版社より印刷会社の方が比較的高額な制作費用となる傾向にあります。出版社の場合は数百万〜千数百万程度が相場となりますが、大手印刷会社などの場合は数千万円かかる場合もあります。
・編集者などのコーディネーターの有無 出版社は編集者が一名、もしくは複数名つき、構成内容のディレクションや制作体制のマネジメント、完成までのスケジューリングまで担当する場合が多いですが、印刷会社に依頼する場合は基本的にクライアント側の担当者がハンドリングを行い、完成物を印刷会社が製本をする、というサービスモデルも多いようです。
・流通機能の有無 一般的に社史・年史は従業員や関係先に配布することを目的とし、一般の書店には流通をさせない非流通型の”インナーブック”として制作することが多いですが、企業によっては周年という記念的なタイミングを活用し、自社の営業・PRをおこなうためのツールとして一般の書店にも流通をさせる流通型のメモリアルブックを制作することも増えています。 印刷会社は基本的に流通機能を持っていませんので、上記の様な目的をもった制作の場合は、社史・年史制作をおこなっている出版社のなかで、流通力に強みをもった会社を選択することが重要です。
・プロモーション機能の有無 出版社は新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、WEBなど様々なメディアとのコネクションを持っていますので、特に流通型のメモリアルブックを制作する場合はそのコネクションを活かしたプロモーションを行うことができます。流通型を選択する場合は流通力の他に、プロモーションに強みをもつ出版社を選択することで、出版後の反響をより大きくすることができます。
次回は社史・年史制作における制作工程とスケジュールについてご紹介致します。
<第三回についてはこちら> 周年記念事業を成功に導く 押さえておきたい社史・年史の作り方【第三回 制作工程編】
幻冬舎メディアコンサルティング
太田 晋平
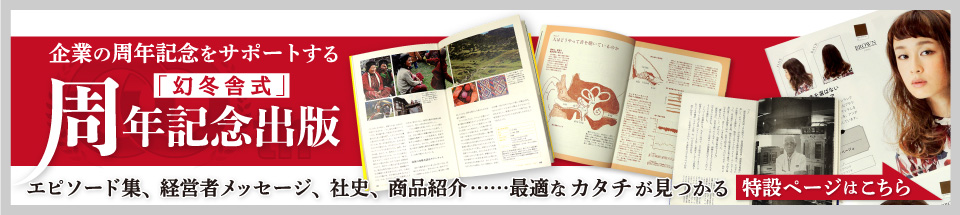
- 【無料ダウンロード】> 企業の周年記念をサポートする「幻冬舎式」周年記念出版 成功ノウハウ&事例集
- 【目的別に見る効果事例】> 社史、周年史をつくりたい
- 【クライアントインタビュー】> ラジオ、雑誌など各種マスコミで紹介! 「書店売りの社史」で自社の強みを再確認。
- 【サービス案内】> 費用の考え方