ブランド再生仕掛け人が明かす どんな企業も陥る「マーケティングの罠」
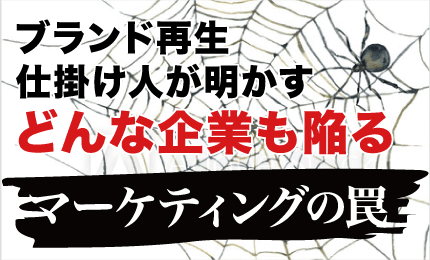
マーケティングには見えない罠が潜んでいる。本記事では企業が陥りがちな「マーケティングの罠」について具体的に見ていこう。おそらく皆さんも思い当たる節があるのではないかと思う。
①自分のことほど分からない
「差別的優位性=唯一性をうまく表現する」ということが最も難しい。 その根本要因は、自分のことを客観的に見るのが難しいように、企業も個人の集合であるので、自社のことを客観的に見るのは難しく、自社の差別的優位性を見誤る、見落とすものであるということだ。
これは人間の根本的な本性に関わる問題であり、どんな企業にも当てはまることである。実際ご支援したすべてのクライアントに当てはまっていた。私は前職でこのことに気づき、「どんな企業も陥りがちな罠から脱出する方法」を開発し、これが今の「潜在価値開発」の源泉となっている。
②顧客も自分のことは分からない
自分で自分の差別的優位性が分からなくともベビーユーザーなら、きっと自社の差別的優位性=唯一性を理解してくれているだろう。なぜなら、実際にお金を払ってモノやサービスを買ってくれているわけだから—。
そのように考えたくなるのが人情だ。ところが実際にヘビーユーザーに聞けば自社の差別的優位性が分かるかといえば、実は分からないのである。皆さんも思い当たるところがあるだろう。自分がなぜその商品を買ったのかと聞かれて、明確に答えられるだろうか。
もちろん聞かれれば、なにかもっともらしいことは答えるかもしれない。しかし、それは真実の答えではないことのほうが多い。「なぜこの商品が選びましたか?」と聞かれれば「機能性が高いから」と答える。
だが、実際にはほとんど無意識でその商品の選択をしているのである。別の言い方をすると、理屈だけでなく感情(そのときの気分やそれまでに蓄積されたイメージ)で選択していくからである。もちろん機能的なベネフィットを詳細に比較検討し選択している人もいるが、ほとんどの人はいろいろな情報収集をしている場合でも最後はなんとなく感覚で選んでいる。
こんな例がある。銀行から依頼されたカードローンの顧客獲得プロジェクトで、実際のカードローン利用顧客のリサーチをしたときのことである。 他のカテゴリーならともかく命の次に大事なお金を借りるのだから、損得をはじめ種々比較検討して、論理的に判断しているだろうと思っていたのだが、実際にはイメージ的な判断をしていた人が多かった。
顧客はあまり比較検討せず「A社で借りるのは怖い、こちらなら安心」というように、論理的な根拠が薄いイメージだけで判断していたので驚かされたのである。
こうした例に見られるようにヘビーユーザーに購買理由を聞き、それを真に受けてもうまくいかないことが多い。本当の理由は深層の無意識の中にあることがほとんどである。 聞かれて答えられるのは表面的な理由に過ぎず、仮に機能的な理由を語ったとしても、実際には無意識の中にある過去のストックイメージ(その企業・カテゴリーについての過去の記憶)に影響されていることが多い。それを読み解かなければ、真実の理由は分からない。
③顧客との見方がズレる
どのような業界にも「業界の常識」とされるものがある。しばしば企業は自分たちの業界の常識でものを見たり判断してしまい、顧客の見方とズレてしまうことがある。
例えば、ある文具のリサーチを行ったときのケースでは、こんなことがあった。文具メーカーは市場は3つのカテゴリーに分かれていて、その中の1つのカテゴリーのシェアを高めたいという意向を持っていた。
ところが実際に顧客をリサーチしてみると、顧客はその3カテゴリーの区分をまったく認識しておらず、すべてを同一のカテゴリーと認識していた。つまり文具メーカーと顧客の見方はまったくズレていたのである。
④市場を概観してしまう
誰しもありがちなパターンとして、「市場を概観して、戦略を決めてしまう」ことがある。マーケティング戦略の立案においても、経営戦略の立案においても同様なことがいえる。
数字で市場伸長率・シェア・販売数量・顧客数を見て方向性を決めることは、一般的に実行されているので何の疑問も持たないことが多いが、市場を数字で概観しているかぎり、多少セグメントしたところで、誰が見ても同じような判断となり、極端にいえば誰もが同じことをすることになる。
そうなると、みんなが同じ方向を向いての同質化競争になり、差別的優位性をつくることができない。
市場を概観ばかりしていないで、実際に市場に手を突っ込んでかき回し(消費者の意識の中に入っていく)、消費者意識調査をするとまったく違う様相が見えてくることが多いものである。
守秘義務があるため、どの業界のどの企業とは申し上げられないが、その企業のあるブランドの販売シェアは5%程度で、市場のトップ2は合せて90%ものシェアがあった。普通に考えれば、その圧倒的な差からこれは勝ち目がないのであきらめるのが概観的な見方である。
ところが実際の顧客の意識に手を突っ込んでみると、トップ2のブランドロイヤリティは販売シェアほど強くはなかった。つまり、先に述べたように「行動ヘビー・マインドライトの法則」に当てはまっていたわけである。
販売シェアとブランドロイヤリティ(顧客のブランドに対する忠誠度)に実際にはギャップがあったのだ。ブランドロイヤリティと販売シェアが強くリンクしていたならやはり勝ち目はないと判断しただろう。
だが、トップ2のあまり高くないブランドロイヤリティを見てこれなら勝てる可能性はあると判断した。そして実際に「潜在価値開発」によってひっくり返すことができたのである。
このように購買行動とマインドが一致していないことは往々にしてあるものだ。そのときこそマーケティング戦略を根本から見直す好機なのである。
また、これは別の業界になるが、「早い」「安い」「簡単」という競争原理で競合が争っていた。概観すればそれが業界常識で、私のクライアント企業もそういう認識をしていた。 業界常識に捉われない私ですら、そんなものなのかと思っていたが、顧客の意識の中に入りこんでみると、まったく違った様相が見えてきた。
その企業の顧客は「早い」「安い」「簡単」などを企業に求めておらず、「安全」「安心」「信頼」を求めていた。その理由としては、その企業が圧倒的な信頼感を持たれていたことによるものだった。そこから、マーケティング戦略を180度方向転換したのである。
⑤反射的・習慣的に考えてしまう
企業で戦略を考える人に共通する反射的・習慣的な思考癖がある。それは、常に「新規顧客・若い年代層」をターゲットにしたがるということだ。
これは、高度成長期のマスマーケティングによる「トライアルユーザーづくり」の思考方法に他ならない。少子高齢化、人口減少時代になっても、反射的・習慣的に高度成長期の先輩世代の思考癖を受け継いでしまっているのではないだろうか。
冷静に考えても、今の若年層は有望な市場ではない。市場規模は団塊の世代の半分以下であり、しかも均一ではなくセグメント化されていて、マスを狙いにくい多セグメント化した層である。なおかつ可処分所得も低く将来の所得向上の見通しも見えないので消費意欲は低い。
そればかりかターゲット層に到達させるためのコミュニケーションチャンネルもネットネイティブ世代であり、SNSなど多極化・複雑化しているので、情報を伝えにくい。にもかかわらず、新規顧客で若い層を狙いたいという企業が多いのである。
中には明らかにシニア層に強い企業が、「新規顧客・若い年代層」を取りたいなどと言う。確かに、データをみればシニア層の浸透率は高く、若い年代層の浸透率は低い。そういうデータを概観すれば、反射的に若い年代層を取りに行きたくなる気持ちも分からないではない。これも前項の市場を概観することによる罠なのである。
浸透率はあくまで平面的なデータである。浸透率は高く見えても、購入頻度が高くないということもある。
高い購入頻度を取っているなら、シニア層は本当に放っておいて若年層に目を向けてもいいのだが、まだまだ取り切っていないことが多い。実際よくよくみて見るとほとんどが取り切れていない。ないものねだりよりも、まず得意領域の得意な顧客をもっと取り切るべきなのである。それがもっとも効果的かつ効率的な行動だろう。
⑥前提を跳ばす
「前提を跳ばす」と言われてピンとくる人はどれだけいるだろうか。「前提」とは、企業が顧客は既に知っているはずと思っている基本的な知識である。しかしここに盲点がある。
顧客、ユーザーと深くコミュニケーションしてみると商品やサービスの基本的な知識を顧客は知らなかった、知らない顧客が多かったということが実に多い。そんなことは当然知っているはずと跳ばしてしまい、うまくコミュニケーションができていない企業が多いのである。
②の「顧客も自分のことは分からない」で述べた、銀行のカードローンの顧客獲得プロジェクトでのことである。対象顧客の調査をしてみると、お金を借りたことがない人はお金の借り方をまったく知らなかったのである。
ご存知の人もそうでない人もいるかと思うが、カードローンという商品は、銀行に融資を申し込み、限度額を設定してもらい、カードローン専用の(他の機能が付随しているものもあるが)カードを発行してもらって、銀行のATMで必要な金額を下すというものである。
そんなことは誰でも知っているだろうと銀行も私も考えていたのだが、そのことを知らない対象顧客は非常に多かったのである。「キャッシュカードでお金が借りられる」と思っていた人も少なくなかった。
そこでまずは、お金の借り方を教えたり、借りるにあたっての不安感を解消する必要があることが分かったのである。
また、ある弁護士事務所のコンサルティングをしていたときには、私は所長に次のようなアドバイスをさせていただいた。
「ほとんどの方はどうやって弁護士へ相談したらいいかをまったく知りません。どこまでが無料で
どこからが有料になり、その後どんな料金体系になっているのか分からない。ですからまず顧客に相談の仕方や料金体系をきちっと教えましょう。そのことが事務所の信用を高め、新規顧客開拓につながりますよ」
実際、皆さんも「弁護士への相談の仕方や料金体系を知ってますか?」と聞かれれば、おそらく即答できないのではないかと思う。私もそうだった。この「前提」を跳ばして顧客とコミュニケーションしてもかみ合うはずもないのである。
こうした現象はどんな業界でもある。「前提を跳ばしてしまっている」ことがあるかもしれない。そういった視点で業界と顧客を見つめ直してみてほしい。新しい顧客へのアプローチ方法が見えてくると思う。
⑦企業の言葉で表現してしまう
消費者の求めているものは自分にとっての便益=ベネフィットである。また、自分の心を動かしてくれる情報である。
しかし、どうしても企業は自らの言葉で機能的、特徴的なことを語ってしまう。あまりに微細な機能の差を語ってしまうことが多い。それは決して顧客の求めている情報ではない。顧客が何に喜び(快の充足の価値)や不安・心配の解消(マイナス解消の価値)を感じるのか。そこを深いコミュニケーションによって探る必要がある。
⑧それらしくつくってしまう
CMにしてもコーポレートスローガンにしても「こういうものはこういう感じ」という固定観念があるケースが多い。
ある企業の企業理念作成プロジェクトを依頼されたとき、当初、日立の「Inspire the Next」のようメッセージをつくって欲しいと要望されたことがあった。
しかしそのようなコーポレートメッセージは既に多く使われている。つまり、それらしいものが欲しいということになる。それでは、ありきたりでメッセージとしてのインパクトが薄く、効果を発揮できないケースが多い。「それらしい」ものとは大きく違うものをつくらなければ自社の哲学、姿勢、想いなどが表現されたものにはならないのである。
化粧品会社なども、「化粧品のCMはこういうもの」という固定観念を持ちやすい。実際「それらしくつくってしまう」CMはあまりにも多く、結局は消費者、ユーザーをつかめていない。「どこかで見た感じのもの」として他の商品とともに埋もれてしまっている。
⑨プロに任せきってしまう
広告やマーケティングの現場でも自分たちは運用・プロジェクト管理しかしていないので、仕組みづくりやコンテンツ制作はプロに任せているというケースも少なくない。
例えばCMの撮影現場を見ていると、制作ディレクターや監督、カメラマンに任せきってしまう。意見があっても相手はプロだからと遠慮して何も言わないことが多い。
しかし、つくっているのは自社のCMである。自社のプロは自社である。制作ディレクターや監督、カメラマンは、CM制作や撮影のプロではあっても自社のプロではない。自社の顧客を深く知っているのは自分たちである。それなのに、その顧客に届ける大切なコミュニケーションメッセージの制作をすべてお任せではうまくいかないのである。
⑩うまくいくかを確かめない
企業が自社で「差別的優位性をうまく表現すること(表現開発)」は最も難しいことであると、既に①で述べた。その理由としては、差別的優位性は自社にとって当たり前と思ってしまい死角になりやすく、うまく表現するためには企業側から消費者側への視点転換が必要になるという二つの難しい要素があるからである。
では、「差別的優位性をうまく表現する(表現開発)」ことを成功させるにはどうすればいいのか。有効な方法が「リサーチ・市場テスト」である。
何事においてもうまくいくか確かめることは、ビジネスモデル・マーケティングのすべての段階で必要である。しかし、すべての段階でこれをきちんと行なっている企業はほとんどないと言っていいと思う。いきなり本格展開しても、たいしてコストがかからないというのであれば、リサーチ抜きにまずやってみるでもいいのかもしれないが、そのような案件はあまりないのではなかろうか。
ビジネスモデルをつくるという段階では、自社の独自解、唯一解をつくらなければならないため、他とは異なる発想、大胆な発想が必要になる。しかし、それを実行する段階では、うまくいくかどうかを慎重に試していく必要がある。
なぜなら、ユニクロを率いる柳井さんが仰るようにビジネスは「1勝9敗」だからだ。ビジネスはいきなりうまくいくものではなく、まず最初はほとんどが失敗するものである。
歴史のある企業であれば、過去の蓄積があるため多少の失敗は吸収する余力はあるが、立ち上げたばかりの企業なら一度の失敗で窮地に立たされる。起業して10年残る企業は10%という事実もそれを示している。にもかかわらず、うまくいくかどうかを確かめることをしない企業が多いのである。
「顧客の求めているものを見つける」という問題の発見・選択(商品開発)の段階では、リサーチを実施されている企業は多い。
しかし「差別的優位性をうまく表現する」というマーケティングコミュニケーションの段階で、「うまく表現できているか」をリサーチ・市場テストをして、きちんと確かめている企業は非常に少ない。ここにもこれまでのマーケティングコミュニケーションが抱える根本的な問題がある。
私が前職のヤクルト本社の広告部長時代、このような表現開発のためのリサーチや市場テストを徹底してやっていたが、「そんなことをしている会社はありませんよ」とよく言われた。ヤクルト本社を退職し、自分の会社を立ち上げて、いろいろな会社を支援してみると、やはりその通りだった。
「差別的優位性をうまく表現する」表現開発はビジネスの中で間違いやすく、難しい領域である。にもかかわらず、それを「これでうまくいくか」確かめていないケースがほとんどなのである。
こちらが意図した通りに顧客が理解してくれないものは、存在しないも同然である。そうなると、せっかく価値あるものを持っていても、それが活かされないことになってしまう。
「差別的優位性をうまく表現する」表現開発が「うまくできているか」をリサーチ・市場テストで確かめ、それから本格展開する。見過ごされてしまいがちだが、もっとも重要なことである。
⑪流行りの媒体ばかり追いかける
マーケティングコミュニケーションにおいてもっとも大事なのは表現である。どんなに優れたビジネスモデルや商品をつくっても、それがうまく表現(表現開発)できていなければ、どんな効果的な媒体を使おうが効果はでない。
にもかかわらず、表現開発が不十分なまま、流行りの媒体、あるいはデジタルマーケティングツールを追いかけてしまうというのが現代の特徴である。
インターネットの普及によって、さまざまなコミュニケーションチャネルが開発され、今までにないようなコミュニケーション手段が生まれてきた。なにか新しいものが登場するとそれをやらないと遅れるという意識で、皆が一斉にそちらに走り出すという現象がここ10年の状況だったのである。
その結果、マーケティングの成果に満足できていないという実情となっている。いうならば、多くの企業が「流行りのもの」に振り回されてきたわけだ。
もちろんそれらは新たなコミュニケーションの可能性を切り開いたのも事実である。しかしそれは「手段」にすぎない。流行りの手段を追いかけている間に足元のことが疎かになっている企業はとても多い。
はっきり申し上げて、そうした現状に気づいているか、気づかずに相変わらず流行りを追いかけているかによって、今後のビジネスの成果はかなり大きな開きが出てくるだろう。
くり返すが、重要なのは「自社の差別的優位性を十分理解し、表現化するか」である。周りが流行りの媒体やツールに乗り出しているからといって、そこだけを見てはならない。
流行りのものはあくまで「伝える」または「コミュニケーション」する手段だ。自分が「なにを(唯一性)」を伝えるべきか明確にし、きちんと表現できてこそ、そうした媒体やツールを使う効果があるのである。
⑫広告代理店に丸投げする
本記事を読まれている皆さんの中には広告代理店の方も多いと思われる。「広告代理店に丸投げ」というワードには反発があることも承知している。それは「罠」ではなく、もともとある構造であり、広告主側もそれを望んでいて、そこに応えているだけという考え方もできる。
お互いに、過程が「丸投げ」であっても、それで結果的にうまくいくのであればそれでいいではないかと思われるかもしれない。
だが、これからの時代(今も既にそうであるが)丸投げ構造ではうまくいかないのである。一昔前の消費者へのコミュニケーションルートが一方通行であった時代、いわゆる4マス(TV・新聞・ラジオ・雑誌)媒体が影響力の大半を持ち、販売チャネルがスーパー・CVS中心というシンプルな状況で、かつ消費者ニーズも比較的均一であればそれでもよかった。
インパクトあるクリエイティブをつくって目立ち、消費者に強い印象を与えさえすれば、とりあえず大きなパイを動かすことはでき、そこからこぼれていっても、また次々と新規顧客が現れていたマスマーケティング時代なら「丸投げ」も機能していたであろう。
だが、現在はいうまでもなくインターネット時代になり、消費者、ユーザーとのコミュニケ—ションルートが多様化・双方向化し、販売チャネルもECなどの拡大によって多様化している。
さらに、消費者の消費経験の深まりや消費に対する価値観の変化などによって、消費者ニーズも多様化し成熟している。
こうした現実があるのに、既存の価値(商品やサービスの機能性や特徴、価格優位性など)をオリエンテーションしただけで企業が広告代理店にマーケティングコミュニケーションを「丸投げ」しているようでは、ビジネスがうまくいかないことは容易に想像できるのではないだろうか。
以上、企業が陥りがちなマーケティングの罠を12の項目に分けて紹介した。 これらに共通していることを総括すると、企業自身が「~しているつもり」という誤った認識を持つことで罠に陥っているといえるだろう。
「自社のことをよく知っているつもり」「顧客と自分の常識は共通しているつもり」といった〝つもり"が誤った方向へマーケティングを導いてしまうのである。こういった認識をなくしていけば、企業はマーケティングの罠から脱却することができるはずである。
こちらのコンテンツは書籍『潜在価値マーケティング』から抜粋しております。

書籍名:潜在価値マーケティング
著者:平野 淳(株式会社ビモクリ)
1981年にヤクルト本社入社。一貫してマーケティングを担当する。1988年マーケティング部発足時に、当時の先端的な理論であったMIT流のマーケティングサイエンスを徹底的に教わる。その結果、缶コーヒーブランド「珈琲たいむ」の売り上げ倍増やトクホ健康茶「爽健美茶」のトップシェア、「ヤクルト黒酢ドリンク」のトップシェア獲得など、目覚ましい成果をあげた。
しかし、その後の実践の過程でマーケティングサイエンスの理論と方法に限界を感じ、ビジネスやマーケティングの本質を追求することによって、独自の「潜在価値開発」理論を生み出す。
2010年に広告部長に就任し、潜在価値開発理論を活用して「ジョア」のブランド広告で、CM好感度飲料部門1位を獲得するなど大きな成果をあげた。
2013年株式会社ビモクリ創業。ビモクリとは「ビジネスモデルクリエイターズ」の略称であり、「ビジネスの新しい理論やモデルを創造することによって、ビジネスの世界を革新する」ことを使命としている。独自のビジネス理論「潜在価値開発®」理論を活用したコンサルティングによって、数々の顧客企業を成功に導いている。
千葉テレビ放送情報番組「ビジネスフラッシュ」、JFM系「マーケの達人」への出演など、メディア取材や講演実績多数。宣伝会議の「ブランドコミュニケーション講座」、「ファンイベント講座」の講師も務める。





