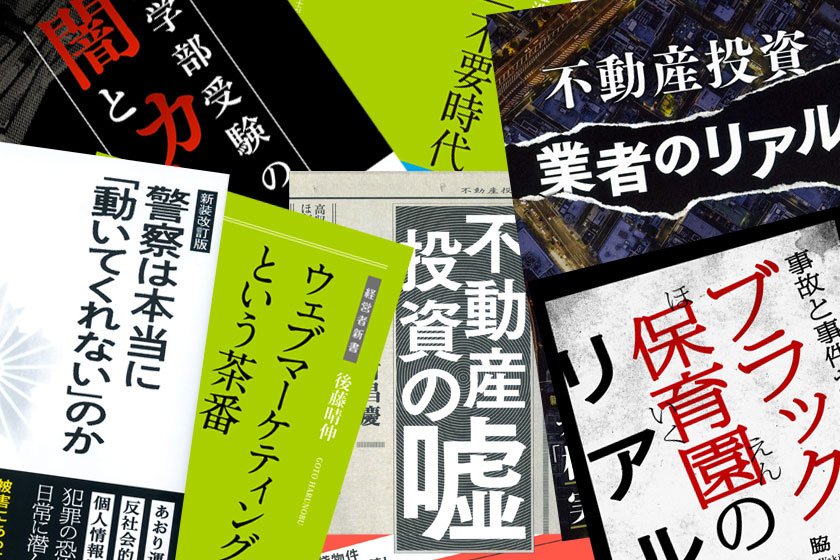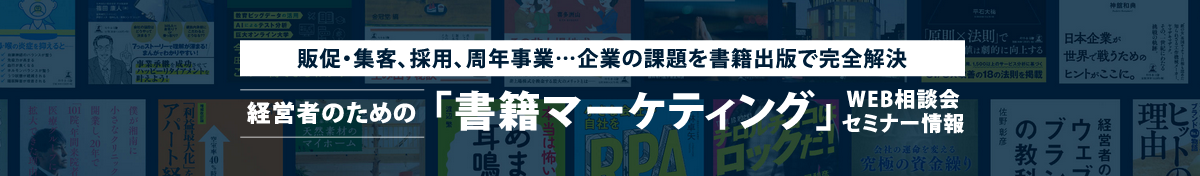消費者の購買行動モデル「AIDMA(アイドマ)の法則」と書籍の関係
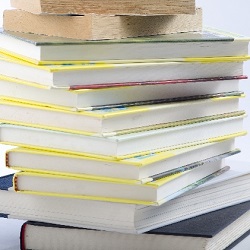
1920年代に米国のサミュエル・ローランド・ホール氏によって提唱された、 消費者が商品(サービス)を認知してから購買するまでの行動プロセスとされる「AIDMA(アイドマ)」の法則。 有名な理論であることから、既に内容をご存知の方が多いかと思います。
各イニシャルが、そのプロセスになっていて、下記のような意味を持ちます。 1.Attention(認知・注意喚起) 2.Interest(興味・関心) 3.Desire(欲求) 4.Motive(動機) 5.Action(行動)
簡単にまとめると、一般消費者が、そのモノ(事)に対して「認知」を行い、自身に関係のある場合は「興味・関心」へと移行します。 その後、興味・関心は「欲求」へと移行し、具体的な実績や内容を知ることで「動機」となり購買や登録といった「行動」へ繋がるということです。
企業のマーケティング戦略においては上記を踏まえ、サービスは認知されているのか?(Attentionの段階)、購入方法が面倒ではないか?(Actionの段階)などを段階ごとに原因分析することで、効果的な施策をおこなうことができると言われております。 さて、その「AIDMA(アイドマ)」の法則を“書籍”に当てはめてみるとどうでしょうか? 結論から申し上げると、 書籍は非常に「AIDMA(アイドマ)」の法則と深い関係性がある と言えます。
1.Attention(認知・注意喚起) →各種メディアでの認知に含め、書店での認知も存在する。 例としては、個人投資家がコインランドリー投資やアンティークコイン投資など、これまで知らなかった投資法を書店を通じて「認知」することが可能です。 2.Interest(興味・関心) →思わず手に取ってしまうような書籍のタイトル。 どんなに良い内容の書籍でも、手に取って読んでもらわないと意味がありません。 各出版社が考えに考え抜いたタイトルは、それ自体に、読者の「興味・関心」をくすぶる効果があります。 3.Desire(欲求) →深い内容を訴求できる書籍だからこそ、消費者の欲求を喚起させます。 文章(ストーリー)を読み込む作業により、その内容が自分の役に立つ(問題を解決する)ことを認識し「欲求」へと変わります。 4.Motive(動機) →書籍の保存性という特徴。 書籍を読んだ段階で即座に行動を起こさない消費者も、家のテーブルやバッグの中に書籍があるだけで、 再度、Attention(認知・注意喚起)、Interest(興味・関心)、Desire(欲求)の一連の流れを思い出させます。 これはテレビやWEB、雑誌とは違う、書籍の“保存性”という特徴であり、消費者があとから行動を起こす「動機」となります。 5.Action(行動) →ビジネス書やノウハウ書籍の多くは、次に起こすべき「行動」指針が示されている。 書籍を読んだ後に、内容通りに実践したり、チャレンジをした経験があると思います。 書籍では行動を起こすにあたっての具体的なノウハウや、サービスの区別の仕方などが記載されている為、迷うことなく行動することが可能です。 以上が「AIDMA(アイドマ)」の法則と“書籍”の深い関係性です。 商品(サービス)の認知向上や集客課題について、幻冬舎メディアコンサルティングでは書籍出版による解決方法のノウハウと実績がございます。 是非一度お気軽にご相談ください。
幻冬舎メディアコンサルティング クリエイティブ局
東 将吾
- 【関連ページ】> アンティークコイン投資 超富裕層だけが知る資産防衛の裏ワザ
- 【関連ページ】> 驚異のハイリターンを生むコインランドリー経営